こんにちは、しょう(@syo5_maint) です。
先日、知人から次のような相談を受けました。
『両親から相続した土地があるんだけど、遊ばしていても勿体ないので駐車場にしたい。駐車場にした場合に駐車出来る台数を調べる為、土地の広さと形を計測したい。土地の広さを計測するには、どれぐらい費用がかかるか教えてほしい。』
土地の計測って凄く難しいと思っている人が多いですが、駐車場の台数を算出するための簡易な計測であれば素人でも計測する事はできます。
今回は、土地の広さと形を計測する方法を素人でも簡単に行えるように詳しく解説していきたいと思います。
素人で十分可能!駐車場用の土地計測【プロ・業者必要なし!】
はっきり言って、駐車場の区割りや台数を算出するために、土地の広さや形を計測することであれば、素人でも結構かんたんに計測できます。
というとプロの「測量士」や「土地家屋調査士」に依頼して、きちんと正確に計測しないといけないって思っている人が多いですが、駐車場用の区割りや台数算出程度あれば、多少の誤差はあっても問題ないので、素人でも計測するのは可能です。
実際に、コインパーキングの運営会社さんであっても、新人の営業マンが現地確認のついでに「ササッと」簡単に計測してレイアウトを作る場合が結構あります。
もちろん、計測した土地に「建物を建築」する場合などは、きっちりと測量をしないと建築そのものが出来ませんので、プロに測量を依頼しないといけません。
駐車場の為の計測であれば、たとえ数cmのズレがあったとしても「駐車場を作ることができない」なんてことにはまずなりません。
運が悪くて最悪の場合でも、台数が1台減る程度ではないでしょうか。
なので、駐車場の区割りや台数算出のために土地の広さを計測するのであれば、ぜひ自分でやってみましょう。
駐車場のプロも使う!簡単な土地の広さを計測する方法を紹介
それでは、素人でもできる簡単な土地の広さの計測方法を順を追って解説していきます。
私自身もこれから紹介する方法を使って、10年以上「月極駐車場」や「コイン式駐車場」のレイアウトを作ってきました。
中には特殊な形状の地形があって計測出来ないものもありますが、大半は問題なく計測することが出来ると思います。
早速、次ののような土地があったとして順番に解説していきます。
紙に簡単で良いので土地の形状を書いてみよう
- 紙
- えんぴつ
まずは、紙に手書きのフリーハンドで土地の形状を書きましょう。神経質になる必要はまったくありません。適当でも大丈夫です。
実際に書く時は、書きにくい現地で記入する事になりますので、綺麗に書く必要はないのでサクサクっと書いてみましょう。
まー我ながら下手くそですが、このように形すら全然違うような四角でも、まったく問題有りません。
ざっくりとした形と「長辺と短辺」がどっちだったか分かる程度で十分ですよ。
メジャーなどを使って辺の長さを測っててみよう
- メジャー
- 巻き尺
紙に土地の形状が書けたら、そこに寸法を測って記入していきます。
慣れてくれば、一人で計測することが出来るようになってきますが、最初のうちは誰かに手伝ってもらったほうが安全です。
プロや業者の方は「ロードメジャー」や「レーザー距離計」を使う場合もありますが、普通のメジャーと巻尺でもまったく問題ありません。
むしろ、アナログなメジャーや巻尺のほうが正確な数値を計測できます。
ですが、ロードメジャーとレーザー距離計を持っていれば、劇的に作業効率はアップするので予算に余裕があれば持っておいても良いと思います。
土地の各部にある辺の長さを測って、土地の形状を書いた紙に記入していきます。
土地の形状によっては辺の数も違いますが、「小学生の時、算数で習った図形」の要領で考えれば分かりやすいかもしれません。
多角形をイメージして、角と辺を可視化すると複雑な地形でも図形として計測していくことができます。
このように紙に書いた図に、測った寸法を記入していきます。
この時、記入する単位については、基本的に「なんでも大丈夫」なんですが業界では通常『㎜(ミリメートル)』を使っていますので、この際合わせておいても良いでしょう。
実はこの単位、建設業では「ミリメートル」で不動産業では「メートル」なんですよ。図面などで見ると違いが殆どわからないので知らない人が多いです。
「、」「.」の違いですね。
「1,023㎜」と「1.023m」の違いです。まーどっちでも良いですが余談です。
今回は四角形なので4ヶ所ですが、複雑な形の多角形であっても辺の数が、増えていくだけでやることは同じです。
角度は必要なし!2ヶ所の角からの距離を測ろう
ここまで辺の長さを計測をして、それを記入してきました。
感の鋭いかたは気づいていると思いますが「小学生の図形」を思い出すと、この図形を書くためには必ず角度が必要だと分かります。
ですが、土地に「分度器」をあてて計測するわけにもいかないので、ここでいったん「中学生の数学」レベルまで意識を上げてもらう必要があります。
ここで詳しくやると長くなってしまいますので割愛しますが、三角形の特性と2点からの距離などを使って正しい図形を書いていきます。
上の図のように、全ての角において、その他の2点の角からそれぞれ距離が分かるように計測する。
要するに『点a』は、その他の点『点b、c、d』の2ヶ所以上との距離を計測する
まず基準となる辺を決める。
基本的にはどれを選んでも問題ありませんが「道路に面した間口」か「一番長い長辺」にしておくと、後々製図するときに書きやすいのでオススメです。
今回は「辺ab」を基準の辺と決めたので、角「a、b」の2点からその他の点までの距離を計測します。
辺の長さを計測した際に「辺ad」と「辺bc」はすでに計測済みなので「bd間とac間」の距離を測る必要があります。
要するに、四角形の場合は対角線の距離を計測します。
複雑な多角形になっても、やることは同じで基準2点から各点までの距離を計測していくだけです。
2ヶ所の点から距離指定すると2ヶ所の交点が出来ます。その一つは線対称で出来ますが明らかに場所が違うので一つに絞り込めますね。
多角形になってもやることは同じですが、数十角など角が多くなると大変な作業になります。
紙にえんぴつと定規とコンパスを使って製図してみよう
ここまで来ると製図に必要な寸法の計測が完了しているので、後はそれを図面に書いていくだけです。
また「小学生の算数」に戻ります。
ひとつだけ注意が必要です。それは効率の良い「尺度」を事前に決めておくことです。
土地の図面を書く事が目的であれば、特に気にする必要はありません。ですが、駐車場のレイアウトや台数の算出をこの後行うのであれば「尺度」の決め方によって、この後の効率が大きく変わってきます。
駐車場のレイアウトを作成する時に使う基準のサイズがあります。
このようにレイアウトの際に土地の図面に「車室や車路」を書きやすくする為に、5の倍数をうまく使ったほうが書きやすくなります。
例えば「1/250」250分の1を使えば、車室を記入する際は「横1cm、縦2cm」、車路を記入する際は「幅2cm」で書くことが出来ます。
土地の広さを考えながら書きやすい尺度をみつけてください。
300分の1などで作成していくと、物凄く書きにくくなるはずです。
例の土地サイズが小さいので、今回は「1/100」100分の1のスケールで作成していきます。
このように、効率の良い尺度を設定していると、後に車室のレイアウトを作成する時に非常に書きやすくなりますね。
基準となる辺abの線を引きます。
15mなので15cmですね。
基準となる線が引けたら、その両端の”a、b”を起点にして「コンパス」を使ってそれぞれの距離の線を引きます。
定規やコンパスを使っているので1㎜単位ぐらいまでしか測れないと思いますので、それ以下のものは大体このあたりかな~ぐらいの感じで大丈夫です。
あとは、コンパスで交わった交点と基準線を定規で線を結べば
敷地図面の完成です。
さて如何でしょうか?
思っていたより簡単に、計測と作図が出来たのではないでしょうか?
実際の土地を用いた、実例をご紹介しようかと思っていましたが思いの外長くなってしまったので実例は又の機会にさせて頂きます。
土地の広さを計測し製図するのに必要な道具一式
習得すると便利なテクニック
ちょっとした距離や長さを道具なしで測るテクニック。
建設業界や不動産業界など様々なところで使われている、体を使って簡易的に計測を行う技術です。
今回は歩幅を利用した距離の計測テクニックです。不動産屋さんや電気屋さんなど距離や材料の長さを決めたりする時によく使っていますね。
計測する機材が手元に無いときや、大雑把にざっくりとした距離が知りたい時に良く使われています。
自身の歩幅を覚えておいて、何歩歩いたかによってその距離を測ると言うものです。
スタートラインを引いて、そこから10歩歩いた距離を事前に計測して、それを10で割った数値を覚えておきます。
実際に計測するときは、自身で歩いてみて、その歩数に歩幅数値をかけるとおよその数値がわかります。
ちなみに私のように長くこれを使ってると、ちょうど1mの歩幅であるけるようになったりもします。
ちょっとしたテクニックですが、覚えておくと便利なときがありますので、是非習得してみてくださいね。
その他、体を使った計測テクニックを紹介していますので、合わせて見てくださいね。
まとめ
さて、今回は少し長くなってしまいましたが如何だったでしょうか。
駐車場にするために、土地の広さを計測するのであれば素人でも、簡単に計測することができます。
また、今後駐車場や土地を事業として行っていくのであれば、これぐらいのスキルは身につけておいて損はありません。
是非、ご自身でこれぐらいの計測と作図はやってみましょう。

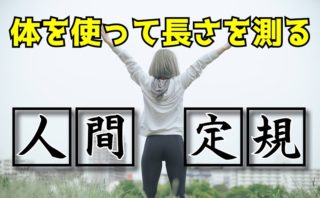
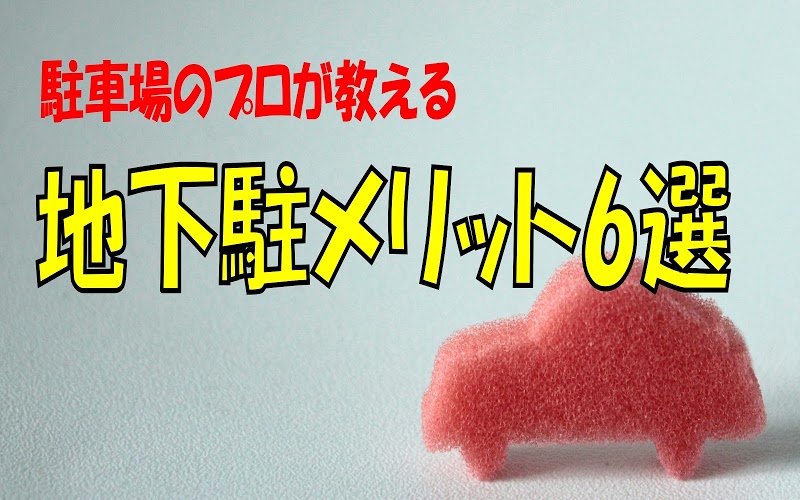
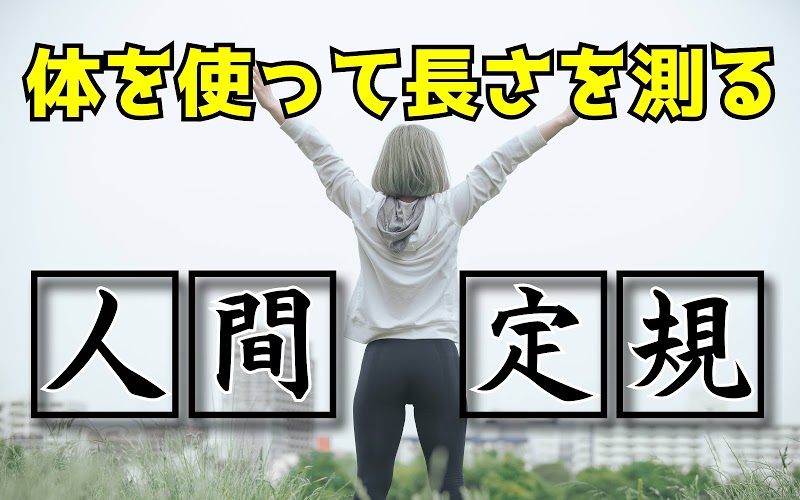
コメント